
目が覚めたら、真上に織田信長がいる。それは日常茶飯事だ。今日も、起きて一番初めに目に入ったのは、織田信長。相変わらず男らしい顔といつものポーズをしている。
しかし、私はベッドの上でつま先立ちして、天井のそのポスターをはがした。ついでに壁のほかのポスターたちも、次々にはがして回った。全て織田信長。 信長尽くしだった私の部屋は、今日、とてもすっきりした。
信長ファンの私にとっては、ポスターをはがして喜んでいるのは信長には少し申し訳ない。でも、今、五年ぶり位に片付いた私の部屋を見ると、驚くばかりだった。真っ白な天井と壁をしばらく見ていた。今日は、私の部屋が真っ白になった記念日だ。
信長にはもう実際に会える。だから、これからはポスターはいらない。とうとうこの日が来たのだ。私は、何も色のない壁を通して、 色鮮やかな南蛮服を着た信長を想像した。初めて会うときには、どんな挨拶をしようか。どんな服を着ていこうか。窓から差す今年初めての春の光に、心を躍らせた。
私は、病気で学校へ行けなくなってから、相対性理論を独学で勉強してきた。相対性理論というアインシュタインの理論を学べば、様々な夢があふれて出てくる。
その一例として、ウラシマ効果。 光速に近い速度で時間をゆがませ、ロケットを未来へ到着させる効果だ。 この信じられないような現象は、昔話の浦島太郎のようにスリップするから、ウラシマ効果といわれるのだ。
しかし、これは未来へ行くための話。 一見すごそうだが、よく考えれば、未来なんて誰でも行けるではないか。現に私たちは、時間が流れている限り、いやでも未来へ歩んでいる。だから、未来より過去に行けることのほうが、価値があるのではないだろうか。歴史好きの私じゃなくても、だれもがそう思うだろう。
科学と歴史が好きな私は、ある時から自然に「過去へ行く」タイムマシンの製作に向かっていった。
心の底から、未来は大っ嫌いだった。 病気もちである私は、よく幼少期を思い出す。 あの頃は自由だったなあ。山へ登って、明るい日差しを浴びていたな。 子供が読めないような本を読んで、よく褒められていたっけな。今はもう自由に走ることさえできない。危機が迫っている私に、もう名誉や楽しさなんてあったって、意味がない。 未来なんてものが来るから、人は死ぬんだ。
だから、私は一生懸命試行錯誤した。 過去に行くためにはどうすればよいのか。ブラックホールとホワイトホールを利用すればよいのかもしれない。エネルギ ーはプラズマ…いや、太陽光を活用してはどうだろうか。自分が乗った時の安全性は?
今まで勉強してきたことを思い出し、知恵を振り絞って研究した。その時、ふと思った。 「小学生なのに、 私ってすごい。」楽しいものを作っているうちに、なんだかわくわくしてきた。ひょっとしたら、私にも名誉があってよいのでは良いのではないのだろうか。
「皆さん、見てください。これが私の発明した、タイムマシンです!」結核を患った少女が、なんとタイムマシンを完成させた。…という風になったら、どんなに名誉なことか。想像するだけでニヤニヤしてしまった。
でも、私は一瞬だらけてしまった自分をすぐ叱った。 私は未来から逃げるために、発明しているのだ。ここで自分が楽しんでいてはいけない。どうせ結核で死ぬんだから・・・。いや、自分の最後なんて想像するものか。私は、今想像していたことを全部掻き消したくて、大声で叫んだ。
気が付いたら、雪山の中にいた。叫びの勢いにまかせて、未完成のままのタイムマシンを、間違って動かしてしまったようだ。だから、時間は変わらず、場所だけ動いてしまったのだ。しまった。病気の私がこんな長距離を降りて帰れるわけがない。しかも、地べたから伝わる雪と上から降る結晶の冷たさが体を包む。
そう思ったのもつかの間、私は自分の部屋に戻っていた。よく分からないが、何らかのバグが起きて、家にまたワープしたみたいだ。助かった。
しかし、あのタイムマシンは戻ってきてはいなかった。中身の自分だけワープしてしまったようだ。 自分が助かったとはいえ、大ショックだった。今まで作ってきたものなのに。でも、私は必ずタイムマシンも回収するつもりだ。絶対早めに回収しよう。
あの山が雪山になっている期間は、山には車で入れない。タイムマシンを回収するには、親に車に乗せてもらうしかない。だから、私は春の訪れを待つのだった。春が来れば、タイムマシンを取り戻せる。タイムマシンが戻ってきたら、パッパと仕上げをしよう。すると、過去へ冒険ができるのだ…!
そして、その日は来たのだった。
ポスターをはがした私は、春の暖かさに包まれていた。いよいよ冒険の始まりだ。
「おもちゃを置いてきちゃったの。」
親もすぐ説得できたので、一安心。
とうとうおもちゃが私の部屋に帰ってきた。戦国時代に行っても違和感のないような、着物を着た。全ての安全確認を終えた後、タイムマシンのボタンに触れた。
ふと目を開けると、夢でも見ているかのような、今までに味わったことのない焦りが体中を襲った。目の前はすべて炎だった。昔ドラマで聞いたことがあるような、足軽のうなり声がものすごい大きさでどよめく。私は本能寺にいたのだ。私の横を矢がかすった。冷や汗が出た。慌てて一刻も早く帰ろうと、タイムマシンのボタンを押そうとした。
しかし、先に誰かに押されたような気がした。私の席の隣に、その「誰か」が乗っている。それをすぐ確認しようとしたが、真っ暗になる。タイムマシンが動き出したのだ。目を開くと、安心感に包まれた。 やっと私の部屋に戻ったのだ。ほっと溜息をつく。 確かめるように、あたりを見回した。天井、壁。全て真っ白だ。ベッドに、使わなくなったランドセル・・・一瞬だけ、すべて変わっていないんだと安心した。 しかし、それは、ほんの一瞬「だけ」だった。
横を振り向くと、人がいた。私は心臓が弾むくらい驚き、退いた。また、何かが降りかかってくる、と思った。
しかし、その人間をよく見ると、豪華な服を着た戦国時代の姫っぽかった。姫といっても、四十から五十代の方らしい。 わたしは、一度目に恐怖で弾んだ心臓を、二度目を興奮で弾ませた。歴史好きが戦国時代の方に会えるなんて、ドキドキして仕方がない。たとえ有名な方じゃなくても、こんな機会はめったにない!記念すべき、初めての歴史人物との対面。私は興奮のままに口を動かした。
「あ、あの。戦国時代の方ですよね!」
「ん?」
「えーと、きれいな着物。お名前は!?」
戦国時代の方が戸惑っているのも気に留めず、どんどん質問をした。名前も聞いてみた。冷静に考えると、本能寺にいた方だったから、きっと織田方の侍女かなんかだろうと思った。彼女は、口を開いた。「わらわはお濃にございます。」
お濃!?まさに驚きの連続であった。お濃は、信長の妻、正室だ。いろいろと謎が多い。
予想以上に有名すぎる歴史人物に出会ってしまった。もう信長に会わなくてよい、と思ってしまうほどだ。
「あの、濃姫ですか!信長の妻の、濃姫ですか!」
「そうにございます。 このお濃に…」
濃姫はしばらく黙っていた。そして、目から涙を流した。
「時間がほしい。」
濃姫は嘆いた。いきなり何を言い出したのだろうか。私は思考回路を急ピッチで巡らせた。そして、川のようにやさしく流れる涙を見て、はっとした。胸に悲しみがぐすっと刺さってきた。そういえば、今は本能寺の変の直後なんだ。濃姫の夫の信長が今頃、炎の中で自刀しているんだ!濃姫と、こんな能天気に話してる場合じゃない。とても申し訳ない気がした。自分が恥ずかしかった。
「ごめんなさい、タイムマシンに乗ってきちゃったんですよね。本能寺…から…」
「大丈夫。」
濃姫は意外にも落ち着いた様子で話した。
「あの方のことは、もう大丈夫じゃ。 とにかく、私に少しの時間がほしい。」
そういった後、彼女は激しく咳をした。そして、彼女の口を押えていた手を見ると、それは血に染まっていた。咳と一緒に、血を吐きだしたのだ…。
濃姫も私と同じ結核病だったとは。私は、自分自身の看病と並行して、彼女の看病もした。彼女とは、日々仲良くなっていった。
彼女は、私とは対照的に、いつも明るかった。夜、私のベッドで寝ずに床で寝ても、心配しないで、と笑ってくれる。
彼女と出会って三日目の夜、私は偶然目を覚ました。その時に、彼女はデスクライトをつけて、こそこそと何かを書いていた。毎晩日記をつけているのだろうか。机にあった鉛筆を使っていたと思う。あの時代なら筆しか使わないはずなのに、まるでもともと使っていたかのような手つきで熱心に描くような音がした。でも、私は眠かったし、声をかける必要もないと思ったので、そのまま目を閉じて眠りについた。
彼女の異能がうかがえるようなエピソードはまだあった。
「そなたが乗ったタイムマシン、よくできておるのう。このボタンをこうやって同時押しして操作すれば、行きたい場所を指定できるはずじゃ。そなたがこう押していれば、あの炎の中にはワープしなかったでしょうに。ははは。」
私が忘れていた機能を、教えてくれた。なんだ、何者だ。不意にそう思ってしまったこともある。
ある時、彼女が言った。
「そなたは、未来が好きか?」
「未来なんて…見たくもない!」
咄嗟に怒鳴ってしまった。
「どうして、見たくのうございますか。 楽しゅう未来が、きっと待っていますよ。」
怒鳴ってしまったのに、彼女はすぐやさしく教えてくれた。でも、私は反論した。
「同じ病気なのに、分からないんですか。だって、どうせ死ぬんですよ。結核ですよ。もう楽しんではいられません。私は悔しい・・・」
「未来は怖いと思えば怖い。けれども怖くのうと思えば以外にも怖くのうものです。」
「嘘だ。」
「怖くなければ怖くない!本当なんだよ、分かって!」
濃姫の口調が乱れた。私はぞっとした。彼女は慌てて言った。
「ごめんなさいね。いきなり。とにかく、明るくなって。」
明るくなんてなれない。
彼女は私の手をそっと握った。すると、魔法のように私の目からは涙が出てきた。彼女の手は、温かかった。部屋中にぬくもりが広がった。そうだ、私は暗いままでは駄目なんだ。でも、明るくなんて…。やるせない気持ちになった。彼女は言った。
「いつか、本当に悲しくなったら、気分転換に、また過去へ行ってみたら。時代はお勧めの時代があるわ。でも、もうそれは設定してあるから。行くときはこのボタンを押すだけでいいわ。」
彼女と出会って五日目の朝。 あのボタンを押す日がこんなに早く訪れるなんて、夢にも思っていなかった。床に横渡った濃姫。体は冷たかった。これが結核の最期の運命なんだ。私は一気に心細くなった。短い間ながらも、今までの彼女との思い出を思い出すと、タイムマシンのボタンを押さずにはいられなかった。
目を開けると、何やら小さい騒ぎが起こっていた。
「誠に申し訳ないが、あの駕籠にどなたか入ってくれまいか。」
戦国時代らしい人が聞いてきた。何が起こっているのか。その質問を理解するためにも、まずは時代を整理しておかねばならなかった。
「今は何年なの?」
こう聞けば、今頃どのようなことが起こっているのかがわかる。
「ぼけているのか。天文十七年じゃ。」
天文十七年というと…。まさか。
「今日は嫁入りの行列じゃ。」
やっぱりそうか。この年に、信長と濃姫は結婚したはずだ。戦国の姫たちは、結婚する際には駕籠に乗って、何日かかけて大名のところに行くのだ。きっとあの籠の中に、お濃が入っている。これから結婚するんだろうな。私は、若いころの濃姫を見てみたかった。
「あの、濃姫はあの中におられるんですよね。」
「おぬしは馬鹿か。 濃姫は死んだのじゃ。 なぜこの騒ぎがわからん。あまり大きな声で言うな。たとえ病気で死んだとしても、ずっと籠を運んでいたわしらが疑われるのじゃ。」
「死んだ?」
「そうじゃ。わしらは悪くないのに、もしも上様にばれてしまったら、どんな罰を受けるかわからん。頼む、時間がないんじゃ。おぬしが濃姫の身代わりになってくれぬか。」
「身代わりに?」
「うむ。」
「これから?」
「うむ。」
「一生?」
「うむ。」
急展開過ぎて、頭が追い付かない。えーと、この駕籠に入ったら、信長がいるところに行って、結婚して…。あれ?もう一回考えてみよう。 この駕籠に入ったら、信長がいるところに行って、けっ…
「早く返事をせんかい。」
「はいっ。」
「いいか、一生ばらすなよ。」
ゆらゆらと揺れる籠の中で、私はやっと落ち着いて きた。同時に不安に駆られた。 私は結核ですぐ死ぬかもしれないのに、本当にこれで良かったのか。信長様に迷惑をかけないか。暗い箱に閉じ込められながら、自分を責めた。
すべて、昔に本で読んだとおりに動いた。この次は新郎の家について、翌日に結婚の儀だったっけな。三々九度はあるのかな。
初めて、あの信長を見た。実際に結婚してみるのは、複雑だった。漫画で見る分には良いけど、実際に会うのは怖い。 もう少し力を抜けば楽しかったのかもしれない。でも私は、自分が楽しむことが許せなかった。
「おぬしは毎日が楽しいか。」
彼は信長らしくないような哀しい口調で言った。私は、昔っぽい言葉を懸命に真似していった。
「私は未来が嫌いでございます。」
「時が過ぎていくのが憎い。毎日を迎えるのが辛い。今日も裏切りを警戒している。我はいつ殺されるのか。びくびくしながら毎日を生きている。我も…我もそうなんじゃ。」
信長はこんな人だったのか?彼のこわばった顔を見て、私は少し疑いそうになった。
「信長様も…。毎日そんな風なのですか。」
「生きるのも怖い。死ぬのも怖い。」
あの堂々とした信長が?私は裏の信長を見てしまった。でも、共感できるものがあったから、緊張が解けた。「私も同じにございます。」
恐れ大きかったあの殿様は、今私の中で、ただの子犬になった。
「みな聞け、また戦じゃ。逆らうものあらば容赦なく殺せ。」
家臣の前では声を張り、いつも鬼のような顔をして言う。
「ははー。」
そして、家臣たちはひざまずく。ほとんどの人が、こっちの信長しか知らない。「信長はうつけものと言われているが、実は鬼のような武将だった」というのはよく知られているが、そのまた裏をかいて臆病だったとは。
でも、戦略的に頭は良いらしく、次々と国を攻め、攻略していく姿があった。彼は笑顔にならない。でも、私はいつも、応援していた。自分の子供であるかのように。
彼は、家督を継いでからも、兄弟とのいざこざを片づけるのに全力を尽くし、義兄との問題も解決させた。私は、改めて、信長ってすごいと感じた。 一度も笑わないから、機械みたいだとも思った。どんどん歴史が進んでいく。彼の手で、進められていく。
しかし、ある時、初めておかしいことが起きた。時は西暦一五六〇年。この時に『桶狭間の戦い』があるはず。しかし、いつまでたっても戦の話がない。
私は、今まで一度も信長の手助けをしなかった。というか、未来人として、過去の人を助けてはいけないと思っていた。しかし、今回ばかりは、つい心配になって言ってしまった。
「信長様。もうすぐ今川がやってこられる。何の支度もしないのですか。」
「考えたこともあったが、やっぱり戦はしない。あの大きな今川だけには、はむかえない。」
「それでは、上洛戦の敗者になってしまいます。どうか、戦の支度をなさいませ。」
信長は、聞かなかった。歴史上だと勝てるのに。私は、イライラして言葉を走らせた。
「少数でも勝てる。私は保証します。信長様なんだから。絶対に勝てるもん。」
「どこにそんな証拠があるんじゃ。」
「まず、大高城と鳴海城の近くに数個の砦を築く。 今川義元がそれらを落として浮かれている内がチャンス。正午ごろに大雨になるから、そのあと桶狭間山に奇襲。」
出来事をすべて話してしまった。
信長は私を頼って大勝利を収めた。世間に名を轟かせたその戦から、彼は徐々に私を頼るようになってきてしまった。信長包囲網の攻略や、本願寺への対策なども、私が手助けしている。 未来からたくさん持ってきた薬を飲んで、寝て、作戦に呼び出される毎日だった。
「未来ではこうなるんじゃな。」
「はい。」
「今日の戦も我が勝ちってことになっているか?」
「そうでございます。」
こんな会話をするようにもなっていた。
二人が四十代後半になったころ。ある夜、彼は言った。
「おぬしは何者じゃ。」
ギクッとした。昔からまさかそんなことを思っていたのだろうか。何を言えばよいのかわからなくなった。でも、設定通りに言うことにした。
「お濃にございます。」
「占い師か。」
「え…?は…はい。」
こう答えるしかなかった。
「我は占いなんか信じない。」
「…。」
「おぬしの勘はひどく優れているんじゃが。」
「占いは、得意にございます。」
「そうか。じゃあ、その占いを、またやってくれぬか。」
「いつもの占いを?」
「そうじゃ。 わしの未来を教えてくれ。」
私は、口を開けなかった。 中国地方へ出陣する途中に、本能寺へ立ち寄る。もうその日が近づいていた。
「違う。ずーっと未来じゃ。死んでも構わない。そのあとじゃ。」
私の心を察したのか、彼はまた言葉を発した。ずーっと未来?分からなかった。でも、寝言を言うかのように、私も変なことを答えてしまった。
「目を覚ましたら信長、壁にも信長。テレビやインターネットでも信長。」
「我は、英雄か。」
「まことに英雄でございます。」
本当に本当に英雄だと思った。 相手の心に届くように、目を閉じて心を込めていった。実際ににそうしているはわからないけど、信長も目を瞑って言葉を受け取っている気がした。
ある日、秀吉から書状が来た。中国への出陣を促す書状だ。ついにこの時が来てしまった。でも、私は、彼の「最期の戦い」を「最期の戦い」ではなくしなければいけなかった。ずっと前から決めていた。
「信長様。今回の中国攻めには、お自らが参加しないほうがよろしゅうございます。本能寺には特に行かれませんように。」
いつものように、生きる道を教えてあげた。すると、 信長もいつものように聞いた。
「今回の選択も歴史上正しいんじゃな。」
いつもと違って、初めて戸惑ってしまった。いつも即答していたこの質問に、今回は何も答えられなかった。私の表情を見ると、彼はゆっくり言った。
「我は、英雄か。」
私は、この前と同じように言った。
「まことに英雄でございます。」
「皆の者、出発の準備をせい。」
彼は言った。いや、まさか。
「おやめください。 中国攻めには行かれないで下さい。」
私は何としても止めようと思った。彼は、死ぬのが怖いんじゃないのか。助けてあげなきゃ。私は、またロを開けようとした。でも、その前に、彼は言った。
「歴史上正しいんじゃろ。」
そして、彼の頬が初めて上がった。初めて笑ったのだ。
私は声も出なかった。彼の頬笑みは、臆病でもなく、鬼でもなく、ただたくましかった。何事も恐れぬような、強い目。これこそ、本当の織田信長だと感じた。確実に変わっていた。いつまでも見ていたかった。
天正八年六月二日、本能寺の朝が来た。気が気じゃない私の心を、信長の笑顔が安定させてくれていた。
突然、彼は起きた。
「あれ、外が騒がしいな。蘭丸、見てまいれ。」
本能寺の外の様子がおかしいことに気づき、彼は部下の蘭丸に、外の確認を命じた。部下は言った。 「桔梗の旗が見えます。あれは多分、明智殿の裏切りです!上様、早くお逃げなさいませ。」
しかし、信長は部下の報告を聞いても、動じなかった。彼は正々堂々と言った。
「是非に及ばず。戦うのじゃ。」
「いや、それでは、上様の身が!」
「我は裏切りなど怖くない。逃げるな。人生の最後まで、前を向いて戦うのじゃ。」
彼は大軍を前に弓を持った。彼の眼は、確実に、前を向いていた。
「寺を燃やせ!」
私が初めて会ったときは、あんなだった。
「おぬしは毎日が楽しいか。」
そしてこう言っていた。
「時が過ぎていくのが憎い。 毎日を迎えるのが辛い。今日も裏切りを警戒している。我はいつ殺されるのか。 びくびくしながら毎日を生きている。」
私は信長たちと、炎の前で弓を持ちながらこう思った。信長は未来が怖くなくなった。死をも恐れなくなった。なぜだろう。激しい戦闘の中で、ぼんやりしている私に彼は言った。
「お濃、もうよい。お前は逃げろ。」
そういって、彼は寺の奥に退き座った。刀を自らの首に押し付けた。
「おやめなさいませ。 死んではならない。」
私は叫んだ。彼は、ゆっくり語った。
「未来を恐れてはならない。おぬしは、それを教えてくれた。歴史上決まっていることなんだ、これは。だからそれから逃げない。」
彼の目は輝いていた。
「怖くなければ怖くない。」
私はどこかで聞いたことのある言葉をさらりと口にし た。すると、彼は言った。
「わしは、英雄か。」
私の目は、涙で今にもあふれそうだった。でも、精一杯、こぼれないように我慢して、言った。
「ずっと、ずっと。いつまで経っても英雄でございます。」
「そう。そのために逝くのじゃ。」
炎が私たちの周りに広がった。溶けてしまいそうな中で、私と彼の中には、確信できるものがあった。後世の名誉のために生きて、逝くのだ。未来への期待を初めて感じた。そういえば、私も久しぶりに笑顔になったような気がした。
彼は、夢の中のような世界の中で、最期を迎えた。
真っ赤な炎の中に一人、懐かしい自分が見えた。私ははっとして、幼い自分の横に座り、ボタンを押した。
目を開くと、真っ白な自分の部屋が見えた。私に驚いた幼い自分。私は、切ないような、可笑しいような気持ちになった。
「わらわはお濃にございます。」
記憶のままにそう言った。幼い自分が、かわいかった。
本能寺の炎の中でためていた涙が、今出てしまった。少しの会話の後で、幼い自分が言った。
「ごめんなさい、タイムマシンに乗ってきちゃったんですね。本能寺…から…。」
「大丈夫。」
私は、ゆっくり言った。信長は、前を向いて生きることができた。
「あの方のことは、もう大丈夫じゃ。とにかく、私に少しの時間がほしい。」
台詞を話すと、激しい咳が襲ってきた。あの時の疲れが今に回ってきたのだろうか、吐血してしまった。
私は毎晩、論文をせっせと書いた。 とにかくこの論文は急ぎなのだ。早く完成させなければ。
久しぶりに鉛筆を持った時、楽しくてしょうがなかった。すらすらと手を動かした。字ではなく、まるで夢を描いているようだった。未来を描いているようだった。
ある時、私は幼い自分に言った。
「そなたは、未来が好きか?」
「未来なんて…見たくもない!」
討論になった末、私は嘆いてしまった。
「怖くなければ怖くない!本当なんだよ、分かって!」
こう怒ってしまったが、そのあとすぐ反省した。でも、幼い自分には未来を好きになって欲しかった。だから、ただ彼女の手を握った。幼いかわいい子は、泣いていた。私は、こう言った。
「いつか、本当に悲しくなったら、気分転換に、また過去に行ってみたら。時代はお勧めの時代があるわ。 でも、もうそれは設定してあるから。行くときはこのボタンを押すだけで良いわ。」
その夜、私はこっそり家を出て、論文を提出しに行った。そして、自信に満ち溢れた足取りで部屋へ戻ってきた。睡眠薬を、湯水のように大量に飲んだ。容器 が空になると、私は満足して部屋の床で寝た。
信長、私へ大事なことを教えてくれてありがとう。 私もあなたのような素晴らしい最期を迎えることができる。未来は何も怖くない。私たちは、死んだ後も、人々の記憶の中でいくらでも甦る。たくさんの思い出の中で生きている。
私が幼い時に自分の部屋に連れてきた濃姫は、自分だったんだ。私は、あの時の私のおかげで、ここまでたどり着くことができた。だから、この幼い自分にまた、バトンを渡してあげたい。私が死んだあとは、きっと、あの時代の、あの駕籠の騒ぎの前に行くよね。
過去で自分はちゃんと学んでいるかな。そして…。未来で自分はちゃんと輝いて英雄になっているかな。
私はこれまでにない達成感を体いっぱいに感じながら、今までの疲労感とともに永遠の眠りについた。
初夏の蒼い空が広がるある日、全国のテレビ画面には、タイムマシンの製造に関する論文の話題が駆け巡っていた。
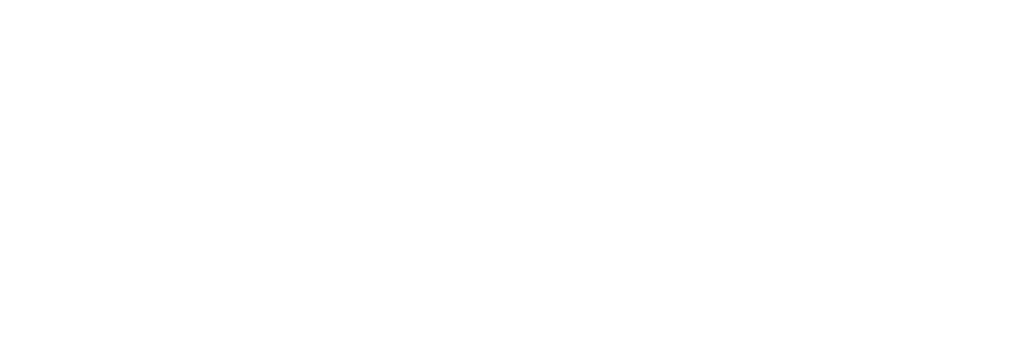



コメント
これは凄い。
伏線の回収の仕方が見事だし、とにかく読んでいて面白い。
生きるとは何かというテーマ性もある。
手塚治虫の火の鳥を初めて読んだ時と同じものを感じました。
過去とゆう未来に行き、未来とゆう過去に戻って来る。
面白いですね。