
未知の世界。それは、喜びや希望だけなのだろうか。そのような綺麗ごとではなくて、悲しみや絶望も詰まっているのかもしれない。私はこの瞬間、そう感じている。 しかし人間、「未知」と聞いたら、鼓動が高鳴るような良い気持ちになる。 イメージするなら、メーターの針の左側が悲しみ、右側に倒れると喜びだとすると、「未知」の言葉の表現を測る時、細い針は、左右に細かく揺れだすだろう。そして微妙に、右へ傾く。目盛りを読み取ろうとすると非常に複雑だが、人は、右のほうに針が近い感情になるだろう。未知の世界が「喜び」だと想像している人が多いという事だ。自分の「そうであってほしい」という願いと、現実が、 同じになってしまっている思想を、誰もが少しは持っているだろう。 未来へのスイッチ。 私はそのスイッチを押しかけたとき、無論喜びへのときめきも感じたが、不安も、ほんの少し心によぎった。 やはり未知の世界は喜びだけではない。押すのを思いとどまった。 私は、普通の人間だった。未知に喜びを感じる単純な人間だった。 しかし、未知の恐ろしさを、不思議な人間に教えてもらった。そのために、スイッチを押すか、押すまいかの迷いが生まれてしまう。されど、そのねじれた心境にイライラして、自分で自分の背中を押すように、無理やり震えた指を押し込んでしまった。 私は押してしまったのだ。闇と光で隠されたスイッチを。 複雑に揺れ、入り混じったものを感情で表したメーターのように。
1
私はある夏、最先端の技術を研究していた。
なんて面白いのだろう。つたう汗も忘れ、科学の研究に取り組んでいた。私は、子供の頃から研究が大好きで、自分で言うのも何だが、素晴らしい功績がある。しかし、私の親友は、私がいくら素晴らしい発明をしようと、あまりリアクションをださない。彼女は、批判は決してしないが、喜びもしない。最高でも、「凄いね」「ほほう」「なるほど」と静かな声で言うだけだ。親友なのだが、時々そこが頭に来る。
しかし、たまに、私に思わぬ助言をくれたり、私の研究を見て鋭い発見をする事もあるのだ。 実は親友は、勉強面ではほとんど、私と肩を並べるほどの成績をもつ。ところが私のような研究などは何もしないのだ。ただ、私の研究をじっと見ているだけだ。私が大きく花を広げる向日葵だとしたら、親友は、私のそばで小さく、可愛らしく咲く、カタバミだろう。
私は、親友が発明の研究をしないのがなぜかは分からない。確かに、研究をする人など少ない。でも、私は研究を親友に勧めているのだ。彼女が研究を始めたら、きっと有名な科学者になるだろう。
私は幾度となく、彼女にそれを勧めているが、彼女は、いつも通りに、冷淡な声で断る。更に、私が発明した物を見せるとき、彼女の声をよく聞いていると、まれに声がゆがんでいたり震えたりしている時がある。そのような時の親友の微笑みは、普段のクスクスッと笑う茶目な笑顔では無く、心の奥に暗いものがまとわりついているような薄黒いものである。
彼女は私の発明が嫌いなのだろうか。
次の瞬間私は、初めて彼女に自分の発明を見せた時の事を思い出した。親友は今と変わらず、真面目な顔で私の発明を見つめた。
「なにこれ、怖い。 私はこういう物は苦手なの。」
と、言っていた。驚き褒めてくれる親友の姿を思い描いていた私は、拍子抜けしてしまった。私は言い返そうと思ったが、相手の顔を見ると、少しこわばった表情だった。その時に、私は彼女の言っていることは全て皮肉ではないことを悟った。彼女の苦手なものを知った。
それからも、何度か彼女に発明を見せることがあったが、あまり大した物ではなくても、チラッと見て不快な表情をしていた。それでは私も不快なので、ある日から、私は彼女には発明を見せないようにした。
すると、だんだん、逆に彼女から、私の発明を見に来るようになった。彼女は発明に徐々に惹かれていくようにして、ついにはいつも私のそばにいるようになってしまい、今に至った。恐るおそる私の作ったものを見ている人間を見ると、若干かわいらしかった。
2
私が過去を思い出しているうちに、あらゆる時に見られる、親友の暗い表情の理由が分かった。私の発明するものが単に恐ろしいと感じているだけだった。しかし、なぜそんなに恐ろしいのか。思い切って聞いてみた。すると、意外にも、長い間封印していたような、まるで台本を読むような口調で、淡々と話し始めた。
「あなたが発明をする。 また発明をする。 どんどん立派なものになっていく。 私はその発明に魅せられ、惹かれていく。 発明されているものは、毎回少しずつ改良され、成長していくじゃない。 そのような時にあなたのような人は喜ぶわ。勿論、私も少し嬉しいんだけれど、私は喜びより悲しみのほうが大きいの。」
「・・・・・なんで悲しみがあるの?」
「あなたが改良することによって、それは徐々に高性能の物になっていく。そして、人間に必要の無い、恐ろしい機械ができてしまったらどうするの?私達の科学技術はここまでで良いの。人間は、科学技術に比例するようには進化できないわ。もしも私達が、人間より優秀なものを生み出してしまったら、私達の未来は無いのかもしれない。」
私は、驚いた。彼女は、溜めていたものを全て吐き出し終えたかのように、下を向き、口をかみ締めた。そして、一度死んだものが再び蘇るように、また少しずつ顔を上げながら、続きを話してくれた。
「私は、それをずっと恐れていたの。どこまで進化するのだろうな・・・って思って。だから最初はあなたの発明が恐ろしい兵器に見えて、近づきたくも無かったわ。でも、あなたの創るカラクリを見ているうちに、それが面白いものだと分かってきたの。あなたは、科学が好きでしょう?」
「うん。」
「わたしも好きよ。」
「え、そうなの・・・?」
私は、仰天した。彼女が科学を好きなんて、初めて知った。逆に、科学が嫌いに見えていた。なぜなら、彼女はいつも、 私の発明を見るときに限って、闇のような表情が顔に走る。しかし、私の中で、今の彼女の「科学が好き」という発言を聞いた数秒後からは、違和感の無い言葉に成っていた。常に発明を見に来るし、とても才能がある。科学好きでも無理は無いだろう。
私は、心の中で、彼女のイメージの中に、科学好きというワードをインプットした。いや、もとからあった、ぼんやりしていた勘の記憶が、浮き上がってきただけなのかもしれない。
彼女は私の発明が好きなのか嫌いなのか。そのギャップが、彼女を不思議なオーラに仕立てていたのだろう。
3
私は、発明に取り組み、最後のカバーにペンチをかけて、曲げた後にばたっと小道具を投げ捨てた。瞬く間に体は飛び跳ねた。
「完成したぞ!」
噴き出すように有頂天になった。ついに多くの人が望む発明を成し遂げた!高さと空間、そして時空を越えた機械を作り上げたのだ。しかも、携帯できるくらいコンパクトな作り。これは世界の次元を覆すような発明品だ。親友は今度こそは驚くだろう。私は恐るおそる、彼女にそれを見せた。
その時、私はそれが見せてはいけない物だということに気づき、目が覚めた。同時に、頭が真っ白になった。
彼女は、後ずさりした。
「み・・・未来予想機!?」
「・・・。」
彼女はとっさに声を出した。
「こんな物使ってはいけないわ!すぐ捨てるのよ!」
私はその通りだと思った。焦って、胸がドキドキした。しかし、その鼓動が語りかけるように、もう一人の自分は、私に反論した。
駄目だ!その素晴らしい機械を捨ててはいけない!
ずっと努力をしてきて作り上げたというのに。
成果と名誉をいらないのか?
大丈夫だ、その機械を使うのだ!
私の気持ちは、境界線から反対側に移動した。私はそこから向こうにむかってこう言ってやった。 「人がせっかく作ったものに、何を言っているの。これは天下の発明品だよ。努力を全部奪っていくつもり?」
今度は、相手が納得したような顔になった。
「ごめん。」
彼女は、私の所から走り去った。
4
そうだ。さあ、スイッチを押そうではないか。未来を覗こうではないか。この機械のスイッチを押せば、今までの努力の成果が見えてくる。希望あふれる未知の世界。私のもう目の前に、自分が生み出した世界が輝いている。この発明はまだ親友にしか見せていないが、世界に向けて見せびらかすのは、まだ早い。少しだけ試しに使ってみよう。
しかし、彼女の言葉が指を止める。本当に押していいのか。もう一度だけ考えてみよう。正しい自分が動こうとした。ところが、私の頭は洗脳されているかのように動きが鈍くなっていた。正しい物事を考えられなかったのは、目の前の輝きが大きすぎたからだったのかもしれない。おかしい、頭が働かない。
早く未来を開きたいと思う気持ちと、もう一回考えなければいけないという気持ちが入り混じっていたが、結局、前者の気持ちのほうが圧倒的に大きかったのだ。
未知の世界。それは、喜びや希望だけなのだろうか。そのような綺麗ごとではなくて、悲しみや絶望も詰まっているのかもしれない。私はこの瞬間、そう感じている。
しかし人間、「未知」と聞いたら、鼓動が高鳴るような良い気持ちになる。
イメージするなら、メーターの針の左側が悲しみ、右側に倒れると喜びだとすると、「未知」の言葉の表現を測る時、細い針は、左右に細かく揺れだすだろう。そして微妙に、右へ傾く。目盛りを読み取ろうとすると非常に複雑だが、人は、右のほうに針が近い感情になるだろう。未知の世界が「喜び」だと想像している人が多いという事だ。自分の「そうであってほしい」という願いと、現実が、同じになってしまっている思想を、誰もが少しは持っているだろう。
未来へのスイッチ。 私はそのスイッチを押しかけたとき、無論喜びへのときめきも感じたが、不安も、ほんの少し心によぎった。 やはり未知の世界は喜びだけではない。押すのを思いとどまった。
私は、普通の人間だった。未知に喜びを感じる単純な人間だった。 しかし、未知の恐ろしさを、不思議な人間に教えてもらった。そのために、スイッチを押すか、押すまいかの迷いが生まれてしまう。されど、そのねじれた心境にイライラして、自分で自分の背中を押すように、無理やり震えた指を押し込んでしまった。 私は押してしまったのだ。闇と光で隠されたスイッチを。
複雑に揺れ、入り混じったものを感情で表したメーターのように。
物を目にした途端、私の心臓は飛び出そうになった。期待でいっぱいだった未来が、一瞬にして崩れ落ちた。 チカチカした文字コードが私の目に焼きついた。映し出された予想は、絶望だったのだ。 どういうことかというと・・・。
親友があと一時間で死ぬ。
私の発明した未来予想機は、でたらめなのか。いや、そうであってほしい。 私の心は灰色に染まった。その機械は偽者だ。信じようとしなかった。一生懸命、頭から事実を突き放そうとした。しかし、いくら追い出そうとしても、無理矢理事実が私の脳に迫ってくるのを抑え切れなかった。
私は長い一秒が経ってから、やっと落ち着いた。理解しようとした。親友の今までの、発明に対する態度や言葉の意味が、胸に突き刺さるように解った。未来を覗く事が、どんなに重い事なのか。科学技術を進歩させていくことは、どんなに危険な事なのか。親友が急に幻に見えてきた。見なければ良かったという感情ではない。もう後戻りはできないという、自分がもう既に死んでいるような気持ちになった。
その時間、私はただ独りで、暗黒の世界で機械と向き合っていた。コンピューターの動いている微かな高い音しか聞こえなかった。それが私の耳には、とてつもなく恐ろしく聞こえた。
詳細を目にする。
「予想時刻、彼女が現在居ル部屋ノ中二、殺人者ガスッテ来ル。」
この「殺人者」という言葉が、酷くくっきり見えた。私はドキッとした。
「部屋ノ扉カラ入ッテ来ル。 殺人者が来夕時二、コノ機械ノサイレンが鳴リマス」
私は、それを見た瞬間から、その小さい物体を地面に叩きつけて壊そうと思った。されど、壊したって未来は変わらないと思い返し、機械を無造作にサッとポケットに入れ、全力で走った。彼女の部屋に行くのだ。
5
自分が走っているときに見た景色は、色が無かった。全て枯れている様だった。この世界が生きていないように見えた。それは、自分が、周りの事なんかどうでも良いと思っていたからかもしれない。しかし、その「周り」とは対照的に、「私」は何故か動き始めていた。夏の小さなカタバミを守るために、必死に駆けていた。体が極度に熱くなっている。ポケットの中で揺れていた機械が、飛び落ちそうになったので、ポケットを抑えて走った。私は、前傾姿勢になった体に誰かが襲い掛かるように、転びそうになった。それでも、ボロボロになってもいい位にダッシュした。
何処の家の何処の部屋に彼女が居るのかはわからない。しかし、私には勘が有ったのだ。私には、彼女が、この世界のもの全てをなぎ倒して、この世界のもの全てよりはっきり見えているような気がしたのだ。そうすると、周辺の物体の何もかもが透明のように思えてしまった。すると、私に見えている物は自分と彼女だけだ。私は、その彼女のわずかな光を頼りに走った。勿論、幻覚。しかし、今の私にとっては、幻覚が現実だ。
走っているうちに、自分が沢山の気持ちを働かせていたことに気づいた。それが勇気に繋がった。よし、絶対勝てる。今回は勝とう。勝つんだ。
私は、更に気味が悪いような血の気に満たされながら、狂ったように正義感を持ち、ひた走った。
部屋の中に居た彼女は、クタクタになって着いた私を見つめて、きょとんとしていた。私は、機械をおずおずしながら取り出して見せた。私は、彼女が驚くと思い、びくびくしながら構えていた。
しかし、文字コードを読み取った彼女は、顔の表情を変えない。何故そんなに冷静なのか。私がそう感じて逆に驚いたとき、彼女は悲しく微笑んだ。
私は、心のひとかけらが無くなったような気持ちになった。彼女は、静かに、ずっと微笑んでいた。その微笑みは、今にも崩れそうだった。それは、私が今まで見た中の彼女の笑いの中で、一番、哀しいものだった。私のがくがくしていた膝は、彼女の感謝の気持ち、お詫びの気持ちを感じ取っていた。彼女は、「さようなら」をささやかに伝えようとしていたのだ。諦めている気持ちは、私にもよくわかった。私は、彼女の気持ちと一緒になり、遥かに静かな部屋で、ただ、最期を迎えようとしていた。機械に表示される残り時間は、あとわずかだっただろう。
6
その時、友人と過ごす静寂の空虚な心地よさを感じていた。しかし突然、私の心中に、正反対の殺気が生まれてきた。まだ諦めてはいけない!・・・その殺気は、前に感じた狂ったような正義感が戻ってきたものといえる。急に戦う気持ちになってきたのだ!私の体には緊張が走り、心は奮いあがった。その気配に、親友は密かに気付いていたのかもしれない。彼女は、険しい顔になった。私の心は、それに構わず闇から立ち上がろうとした。例の文を思い出した。
「予想時刻、彼女ガ現在居ル部屋ノ中二、殺人者ガ入ッテ来ル。」
「部屋ノ扉カラ入ッテ来ル。 殺人者ガ来夕時ニ、コノ機械ノサイレンガ鳴リマス」
私は、もうその「殺人者」を殺すしか無いと誓った。体がギシギシいっている。やる気。いや、殺る気になってくる。私は、 これが本物のゲームだと悟った。
そこでふと、私に疑問が生まれてきた。
勝つか負けるか、あの機械で未来を調べられるのではないか。
けれども、私は直ちに、何かを振り落とすように首を横に振った。正々堂々と勝負をする。私は、機械に目をやらなかった。懸命に前を向こうとする。それは、何かが怖かったからなのかもしれない。
すると、親友は、気持ちが変わったように言った。
「あなたは殺人者に勝てるわ。」
私は、その言葉を聞いて、やっぱりそうだ!と思った。 そして、なぜか、私が親友を未来予想機の様に信じていたことに気が付いた。世界で一番、信頼出来た。そうだ、私は「殺人者」に勝てる。絶対そうだと思った。
私は必ず自分の手で「殺人者」を殺す。
また、親友は、再び口を開いた。
ページ紛失 概要 二人は、殺人者を倒すための武器を話し合って、キッチンのナイフに決めた。ところが、親友の家には、ナイフが1本しか無かった。しかし、主人公は、彼女が持つ護身用ナイフと、自分が持つであろう攻撃用ナイフ、2つが必要だと考えた。そのために、主人公は攻撃用のナイフを自宅に取りに戻ることにした。親友の心配をよそに、主人公は自宅への道を、再び全速力で走りだした。
7
一方彼女は勇者を待っていた。しんとした部屋で、じっと待っていた。必ず来ると、信じていた。
次の瞬間、サイレンが鳴った。
びくりとした後、彼女は心の奥で、こうささやいた。
あなた、間に合わなかったのね。でも、大丈夫よ。
あなたの気持ちをこれに乗せて・・・
彼女は、サッと手にナイフを持ち、ドアの方向に構えた。緊張が走った。 ウーウーとサイレンが鳴り響く。
「ガチャ」
ドアの開く音がした。彼女は、とっさに、息を切らし出てきた「殺人者」にナイフを投げた。しかし、殺人者は、慌ててそれを避け、闇雲に新しいナイフを投げ返した。 ナイフは、彼女に直撃した。
彼女は、ばたりと倒れ、赤いものを流し、微かな音で殺人者に気持ちを伝えた。
このナイフ、あなたのナイフね。
私は、世界で一番、「殺人者」を愛しているわ。
私は、楽しかったわ、「未知の世界」。
あなた、殺すのかしら・・・?殺人者を・・・でも・・・
彼女は、途中で、何も喋られなくなった。死んだ。
最後の言葉の意味が、分からなかった。それはともかく、その前の言葉。私には、楽しそうに聞こえなかった、彼女の言う「未知の世界」が。 別の意味に聞こえた。
私は、彼女の言葉を聞いて、今にも泣きそうになった。
先刻、私が彼女のドアの前に来たとき、サイレンが鳴った。「殺人者」がもう中に入ったのかと思い、すぐ戸を開けたら、 ナイフが飛び掛かってきた。私はそれを避け、自分のナイフを相手に刺した。しかし、私が刺したものは「殺人者」ではなかった。「殺人者」は、その部屋の中に居なかった。なぜなら、「殺人者」は、自分自身だったからだ。
殺してしまった。消してしまった。失くしてしまった。彼女の心臓の音が静まっていく事に反比例するかのように、私の心臓は狂ったように速まっていった。私は、今度は、既に息が詰まって死にそうな気持ちでいる弱気な自分を、本当に殺してやろうと思った。 沢山の言葉が心に蘇り、響いてきた。
「予想時刻、彼女ガ現在居ル部屋ノ中二、殺人者ガ入ッテ来ル。」
「部屋ノ扉カラ入ッテ来ル。殺人者ガ来夕時ニ、コノ機械ノサイレンガ鳴リマス」
「あなたは殺人者に勝てるわ。」
「あなた、殺すのかしら?殺人者を・・・でも・・・」
そう。殺す。仇を討つのだ。彼女は最後、私に自殺して欲しくないと伝えたくて、言葉を出したのだろう。しかし、私は、親友のナイフを拾い、自分に突きつけた。そして、勢いをつけた。
未知の世界。 それは、流れる血に光る、友情の物語なのであった。
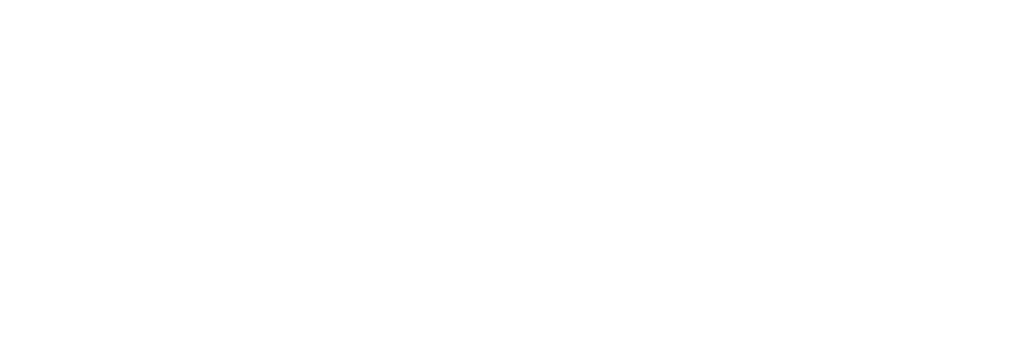


コメント
親友が懸念していたのはこれだったんですね。
親友の「私は、楽しかったわ、未知の世界」
の解釈は難しいですね。
メーターの針が左側に傾いていた親友が最後には右側に傾くということなのかな。
逆に「私」は傾きが右側から左側に変わるみたいな。
文章的には5の段落の親友の部屋に向かって全力で走っていく箇所の表現が秀逸ですね。